東京大学の推薦入試の条件、基準が一般入試よりも難しい!
公開日:
:
その他の話題
今朝の朝日新聞の一面に載っていたのだが、東京大学で推薦入試を始めるらしい。推薦で入学できるのは、全学生のうちの3%程度に当たる人たちらしいのだが、3%といえども、今後は推薦で東大に入れるらしいですから、東大生の見方も変わるかもしれない。企業からしてみれば、推薦だろうが関係ないと思う場合もあれば、推薦やAO入試など、一般入試じゃない学生を排除しているところもあるから、一般入試で入った学生まで推薦で入ったのではないか?という目で見られるのかもしれない。ただ、朝日新聞の情報によると、推薦入試のその条件が些か厳しい。というか、むしろ一般入試よりも推薦入試の方が難しいだろ!(笑)とも思えてくる。定員が少ないので、その点についても十分難しいのだが、何よりも試験の内容が難しいのです。倍率も高くなりそうですから。
推薦入試でも結局学力は必要という見方
これは現段階のことであって、恐らく決定ではないのかもしれないが、推薦入試を受けられるのはそもそも1つの高校から男女1人ずつらしい。そして、高校での成績とかも見られるのかもしれないが、グループディスカッションや面接を行うことになっているらしい。このあたりは予想がつくでしょう。こういう人物試験については、公平なジャッジができないだろうという批判がある。それは個人的には同意だが、一応推薦入試は全体の3%程度なので、そういう運ゲーが嫌ならば、一般入試を受ければ良いのだろうから、そこは大した問題には思えない。そして、意外だったのは、推薦入試であっても、センター試験を受けないといけないというのです。センター試験で8割以上の得点が必要らしい。これは結構厳しいぞ、結構科目数が多いから、それらの科目でトータル8割というのは、結局私立大学でいえば、マーチには余裕で受かるくらい、早慶上智にも手が届きそうなくらいの学力がないと厳しいのではないか?と思えてきます。
私は東大とかも含めて、国公立大学を目指したことがないのであまりよく知らないが、普通の東大の入試の場合には、センター試験が8割というのは恐らく少ないだろう。9割近くとっておくのが理想と言われるくらいだったと思います。足きりさえ通れば良いという見方もありますけどね。だから、従来のハードルは低いが、5教科7科目必要と言われているセンター試験で、8割以上をとるのは非常に難しい。3科目に直したら9割以上必要な数字なんじゃないか?と思えてくるが、そうなればセンター利用でマーチ上位学部も全然受かるレベルに思えてきます。9割だとセンター利用で早慶は厳しいが、一般入試では可能性はあると思う。つまり、一般入試でマーチ~早慶くらいに受かる学力がないと結局推薦は通らないとなれば、学力を一切軽視しているわけでもなさそう。というか、案外、学力以外の部分も往々にして見られているという意味では、難易度は一般入試よりも高いのでは?と思えてきます。特にグループディスカッションや面接っていうのは、勉強みたいに努力でどうにかなるものではないので、こっちの方が普通に厳しいでしょう。
「多様な人材」とはそもそも何か?
東大が推薦入試に踏み切る理由は、多様な人材を集めたいという狙いがあるらしい。私はそも目的を見て些か疑問を感じた。それはそもそも多様な人材の「多様」ってナンだよ?と思う。人材の多様化を目指して東大が推薦入試をやるなら、そもそも今のやり方で多様な人材がとれないのか?を説明してほしいし、それ以前に多様性の定義がよく分からないから、それも説明してもらいたい。どういう人たちが集まったら多様化していると言えるのでしょうか?朝日新聞には、世界で活躍する市民的エリート」なる字が躍っていたが、つまり、国内のみではなく、世界に視野を持った人材を育てたい。育成したいという思いがあるのか?と窺えるが、それは多様化を示すのだろうか?現状が多様化していないっていうことなんだろうけど、現状だって世界的視野を持った人材はいると思うんですけどね。その割合を増やしたいってことなのでしょうか?仮に現状が学問、研究、卒業後の進路などで国内を優先したり、就職したりする学生が多くいて、世界に目を向ける学生が少ないとして、それが一極化を示しているのだとしたら、世界的規模で活躍する人材を増やしたところで実現するのは多様化じゃなくて、二極化じゃないのか?と思う。私は現状でもある程度は多様化していると思うよ。というか、何を持って多様化しているという見方をするか?の違いであって、多様化しているという見方もできなくはないと思う。世界で活躍する人材を確保すれば多様化しているといえるならば、現状でもある程度は多様化は実現している気がするんだ。逆に現状で多様化になっていないというのならば、世界で活躍する人材を集めたところで、それは多様化じゃなくて、二極化じゃないのか?と思うのです。
そして、もう1つ言いたいのは多様な人材を確保したいというやり方が、どうして入学試験の時点から行われるのか?がよく分からない。私に言わせれば、センター試験は推薦入試でも受けるわけだから、一般入試と推薦入試の大きな違いは人物試験の有無ですよ。人物試験を突破してきた人たちは、一般入試で入ってきた学生らとは違う視点を持っているという認識なのかもしれないが、それは本当だろうか?と思う。だって、一般入試で入ってくる人たちは面接とかやらないわけですよね?つまり、彼らの視点や考え方っていうのは一切入学前には分からないわけだ。そうなると、推薦入試で入ってくる学生の視点や考え方は判断できても、一般入試のそれは判断できないから、この2つの入試方式で入ってくる学生にそもそも違いがあるのか?って比べようがないのでは?と思います。だから、推薦入試でとってきた学生のタイプが、実は一般入試で入ってくる学生にも多分に含まれているということもあるのでは?と思います。そうなると、わざわざ推薦入試をやる意味がないとなる。私は多様な人材の確保というのは、別に入学試験の段階からやらなくても良いだろうと。大学4年間を通して、いろいろな人材に育て上げれば良いのでは?と思います。逆に入試の時点で多様性のある人材を確保しないといけないとなれば、大学の中でそういう人材を育てることができないという白旗を上げている状態に近いのではないか?と思えてきます。私は入学試験で確保しようとしても限界があるのでは?とすでに述べているのだが。今後、どういう動きを見せるか?はワカラナイものの、東大が推薦入試を実施するというのは画期的だし、実施に向けて最終的にどうなるのか?注目していきたいと思います。
関連記事
-

-
早稲田大と上智大のレベルはどっちが上で頭いい?イメージや雰囲気の比較と就職の違い
早稲田大学と上智大学はどっちが上でしょうか?どちらも私立大学の中では非常にレベルが高い、難し
-

-
青山学院高等部の偏差値や倍率などのレベルは?進学実績や評判、口コミはどんな感じ?
青山学院高等部は東京都渋谷区にある男女共学の私立高校です。最寄駅は東京メトロ半蔵門線、千代田
-

-
亜細亜大学のキャンパスの立地条件や学生の評判、口コミと就職実績や就職支援の魅力について
亜細亜大学というと、何が有名か?と言えばいろいろな評判があると思います。私の印象ですと芸能人
-

-
神奈川県立麻生高校の偏差値や倍率などのレベルは?進学実績や評判、口コミはどんな感じ?
神奈川県立麻生高校は神奈川県川崎市麻生区にある男女共学の公立高校です。最寄り駅は小田急小田原
-

-
毎日が忙しい短期大学に行く意味は?メリットやデメリットで短大に行く価値や理由を判断しよう
短期大学というのがありますが、これは2年間で卒業のため、4年間ある四年制大学と比べるとあっと
-
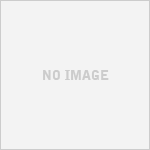
-
広島大学の立地条件や雰囲気と学生の評判や口コミ、就職実績や就職状況のデータはどうなっている?
広島大学のキャンパスというのは非常に広大な面積を誇っている気がします。かなり広いのです。広島大学は国
-

-
年金が破綻する時期はいつ?将来どころか既に破綻している
年金制度は崩壊するのか?するとしたらいつ崩壊するのか?ということは以前から言われています。年
-

-
國學院高校の偏差値や倍率などのレベルは?進学実績や評判、口コミはどんな感じ?
國學院高校は東京都渋谷区にある男女共学の私立高校です。最寄り駅は東京メトロ銀座線の外苑前駅で
-

-
出席をとらない大学の授業を欠席、サボるのは普通、合理的な行動である
大学の授業って、出席をとる授業もあれば、とらない授業もあります。したがって、出席をとらない授
-

-
開智高校の偏差値や倍率などのレベルは?進学実績や評判、口コミはどんな感じ?
開智高校は埼玉県さいたま市岩槻区にある男女共学の私立高校です。最寄り駅は東武野田線の東岩槻駅





